2020年代に入ってから、デジタルの世界が急成長しています。
まさに、「デジタルネイチャー」時代。
人の心の内にあるニーズを、声に出さなくても、読み取ってくれる時代になってきました。
好みのチャンネルはつけてくれるし、気になる新製品やニュースは教えてくれるし。
ぼくも、毎日時代の波の中をフワフワと生きています。
そのように、現在「マイクロマーケティング」の戦略が多く見られます。
現代では、「マイクロマーケティング」は有効なマーケティング手法です。
そもそも「商売」とは、強みがあってこそ成り立つものです。
それを全面に打ち出す「マイクロマーケティング」
「マイクロマーケティング」が強い理由についてまとめてみます。
「マイクロマーケティング」って何

「マイクロマーケティング」とは、小規模なターゲット市場にフォーカスし、その市場に特化したマーケティング戦略を実行することです。
従来のマーケティング戦略では、大規模な市場全体をターゲットとしていました。
そのため、広告や宣伝などのマーケティング活動を全体(全員)に向けて展開することが一般的でした。
しかし、マイクロマーケティングでは、より「狭い範囲の市場」をターゲットに絞ります。
「狭い範囲の市場」つまり、コアな層の人たちです。
その市場に特化した戦略を採用することで、より効率的なマーケティングを展開することができます。
また、コアなファン層なので、リピート率も期待できるというわけです。
「マイクロマーケティング」の重要なポイントは、パーソナルデータに基づくことです。
個人の「属性」や「行動」に基づいて、それぞれの顧客に最適なプロモーションを提供していくことです。そのため、データ分析やテクノロジーを活用し、個人データを収集、解析し、ターゲティングしていくことが必要です。
現在、「マイクロマーケティング」は、インターネットやソーシャルメディアなどのデジタルマーケティングの進歩により、より細分化した形で実現されています。
(僕も、そのマーケティング受けながら日々を過ごしている、といった状態ですね)
SNS等のプラットフォームを使用することで、狭い市場に対してコストパフォーマンスの高い効果的な「マーケティングキャンペーン」ができるといったところが最大の強みです。
「マイクロマーケティング」のメリットとデメリット
次に、「マイクロマーケティング」のメリットとデメリットについて見てみます。
「マイクロマーケティング」のメリットは
安定した収益化を狙える「マイクロマーケティング」のメリットについていくつか紹介します。
ターゲット市場への直接的なアプローチができる
マイクロマーケティングは、より小規模な市場をターゲットとするため、より直接的なアプローチができるようになります。
これにより、よりパーソナライズされたメッセージングが可能になり、効果的なアプローチができます。
効率的なマーケティング活動ができる
大規模な市場全体をカバーするよりも、より小規模な市場をターゲットとすることで、より効率的なマーケティングキャンペーンを実施することができます。
これにより、広告コストを削減することができます。
より高いROIの実現
より小規模な市場をターゲットとすることで、より精度の高いターゲティングが可能になります。
潜在的に可能性のあるターゲット層にプロモーションすることで、高いROI(投資対効果)を実現することができます。
「マイクロマーケティング」のデメリット
では反面、デメリットについてどうでしょうか。
考えられるデメリットについてまとめてみます。
ターゲット市場が限られる
マイクロマーケティングは、より小規模な市場をターゲットとするため、ターゲット市場が限られることがあります。
安定した収益が実現できる可能性の半面、成長の可能性が限定されることがあります。
キャンペーンのカスタマイズが必要
マイクロマーケティングでは、より小規模な市場をターゲットとするため、キャンペーンのカスタマイズが必要です。
万人が求める内容ではなく、コアなファン層に響く内容のキャンペーンを打ち出すことが重要です。
キャンペーンの作成にかかる時間と費用が増加することがあります。
システムやプロセスが必要
マイクロマーケティングを実行するには、ターゲット市場の情報を収集し、解析するためのシステムやプロセスが必要になる場合があります。これにより、追加のコストがかかることがあります。
「マイクロマーケティング」による成功事例

「マイクロマーケティング」による成功事例は多数あげられています。
企業の成功事例をいくつか紹介します。
ニコン
カメラメーカーのニコンは、デジタル一眼レフカメラのターゲット市場を女性に絞りました。
女性が撮影した写真を使用し、マイクロマーケティングキャンペーンを実施しました。
このキャンペーンによって、女性の心理的側面にアプローチすることに成功し、女性市場でのニコンのシェアを大幅に拡大しました。
現在でも「初心者の女性向けにおすすめのミラーレス・一眼レフカメラ」などとターゲットを絞った商品の開発販売を行っています。
パンドラ
1982年創業、デンマークのジュエリーメーカーのパンドラは、独自のブレスレットシステムを開発し、顧客ユーザーのスタイルに合わせてチャームやビーズをカスタマイズできるのが、魅力の会社です。
パンドラでは、購入者に向けたマーケティングを展開しています。
この購入者向けのキャンペーンは、購入した商品に基づき、パーソナライズしたプロモーションアプローチを展開しています。
これは、購買意欲にリーチするだけではなく、顧客満足度が向上し、顧客ロイヤリティが向上するといった効果も見られています。
さらに、パンドラのGMは、今後のマーケティング手法についても、「デジタルやSNSに重きをおきながら、リーチできる客層を広げていく」とコメントしています。
ブレスレットだけでなく、リングやペンダントなどの商品情報も提供できますね。
これも「マイクロマーケティング」手法を効果的に使った一例です。
キア(Kia)
キアは、1944年創業、韓国を代表する大手自動車メーカーの一つです。
キアのマーケティングは、若年層をターゲットに展開されました。若年層向けの動画プロモーションを使用し、SNSを中心に広告展開。
品質も良く、デザイン性に優れている自動車を提供しているため、若者への市場が拡大しました。近年では、電気自動車の開発にも力を注いでおり、今後さらに幅広い層からの支持が期待されます。
ベネッセ
ベネッセは、子育て中の親をターゲットにマイクロマーケティングを展開しています。
ベネッセのキャンペーンは、子育てに関する情報を提供し、親が育児について悩んだときに、ベネッセの教材を選ぶように勧めています。
ベネッセのターゲティングは成功し、子育て世代の親からの支持を獲得しています。
例えば、こんな活用アイデア

マイクロマーケティング手法を旅行業者がすると仮定して、いくつか提案してみます。
パーソナライズされた旅行プランのサービス
顧客のデータを収集し、データに基づいて顧客の好みの旅行プランを提案します。
例えば、お客様が好きな、アクティビティ、食べ物、行動スタイル、予算案等を調査し、それに応じたプランをピンポイントで提案します。
全体へのプロモーションはせず、ターゲット層を絞ってマーケティング活動を展開します。
ソーシャルメディア活用によるプロモーション
旅行に関する情報を提供するために、SNSを活用します。
例えば、InstagramやYouTubeなど、視覚的にアプローチできるコンテンツがPRには良いでしょう。
Instagramを活用して、美しい景色や絶景スポット、またはパワースポットなどをアピールすることで、その地域への興味を喚起します。
さらに、特定の旅行体験や旅行情報を配信したり、地域密着型のコンテンツをアピールして、その地域へのトラベルを促したりできます。
興味がわいた顧客が、すぐに広告をクリックできるように、そばにリンクを貼っておけば、顧客誘導の動線が生まれますよね。
マイクロマーケティング広告を配信する
旅行業者は、広告を配信するときに、ターゲット市場を明確にすることができます。
細分化された市場に対して宣伝することで、効果的な広告が打ち出せます。
例えば、FacebookやGoogleAdWordsを活用し、地域や年齢、興味に基づいて特定の顧客に向けた広告展開ができます。
GoogleAdWordsでは、キーワード選定も必要になってきますが、それによって、一層成約率の高い顧客へアピールすることができます。
顧客フィードバックを活用した改善ができる
顧客が旅行中に感じた不満や要望を取り入れることです。
その旅先での「課題」となるものを解消し、顧客満足度を向上させることができます。
フィードバックは実体験に基づく提案なので、改善策が取りやすく効果が上がりやすい点が最大のメリットです。
アンケート調査や顧客レビューの分析によって、サービスの改善点を把握し、それに応じた改善策を実施していきます。
「マイクロマーケティング戦略」が伸びる理由 まとめ
「マイクロマーケティング戦略」が伸びる理由についてまとめました。
マイクロマーケティングの戦略は、ペルソナ(ターゲット設定)がとても重要となります。
ターゲットをより具体的にイメージし、成約見込み率の高そうな層へアプローチしていきます。
現在の日本ではネットやAIの普及により、マイクロマーケティング戦略がより細分化された形で行われてきています。
このマーケティング手法を活用することで、今よりコスパの良いマーケティングを展開していけます。
320
〈あわせて読みたい〉
-
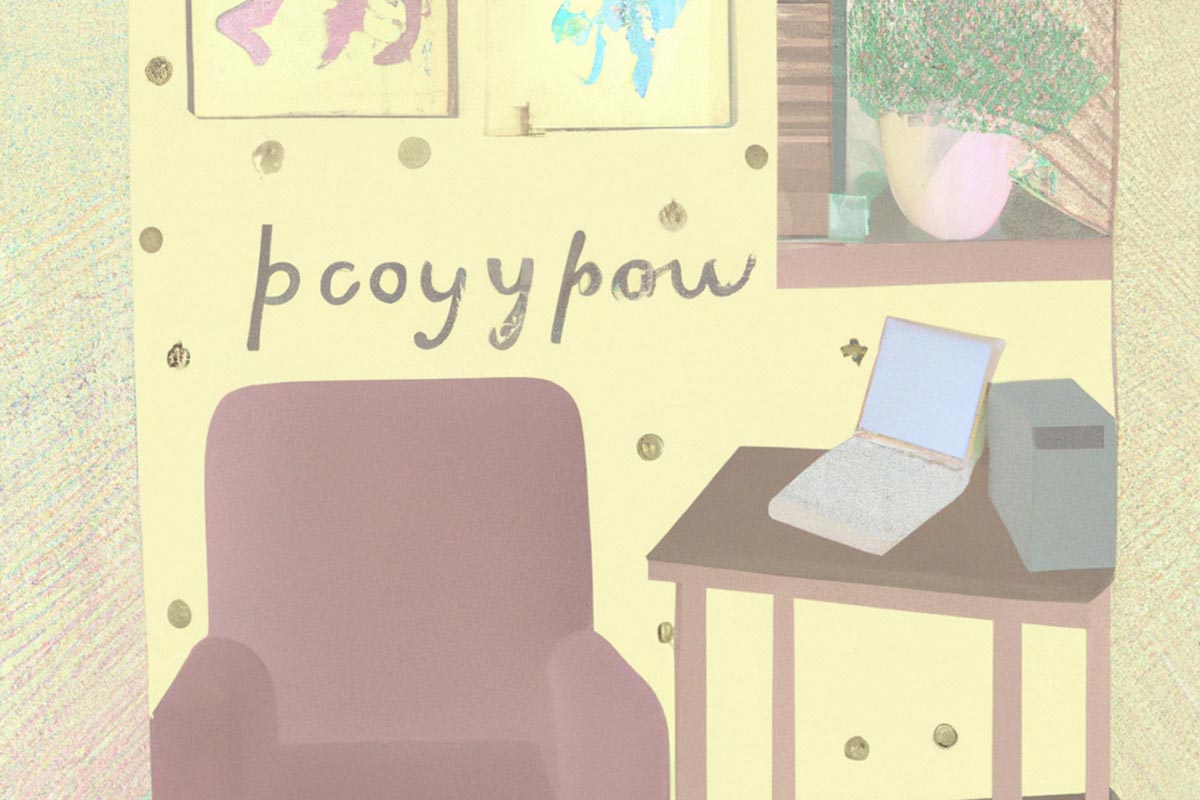
-
デザインの心理学【人の本能へ向けて】
デザインするとき、 レイアウトや配色などがすっきりしていて、見やすい、などということは当然大切なことです。 しかし、デザインの基本的なこと以外にも、実は大切なことがあります。   ...
続きを見る



