「オムニチャネルマーケティング」って、あまり聞かない言葉かも知れません。
でも、2000年以降普及し、2020年以降の今、企業は無視できない手法です。
消費者は、知らず知らずにこの「オムニチャネルマーケティング」に接触しています。知らないうちに接触しているからと言って、悪い手法ではありません。
消費者の「満足度」を高めるための方法です。
最近は、デザイナーの仕事も「オムニチャネルマーケティング」の一部、って感じになってきました。
今回は、そんな「オムニチャネルマーケティング」について紹介します。
Contents
ひらめき勝負!「オムニチャネルマーケティング」って何?【負けない仕組みづくりとは】
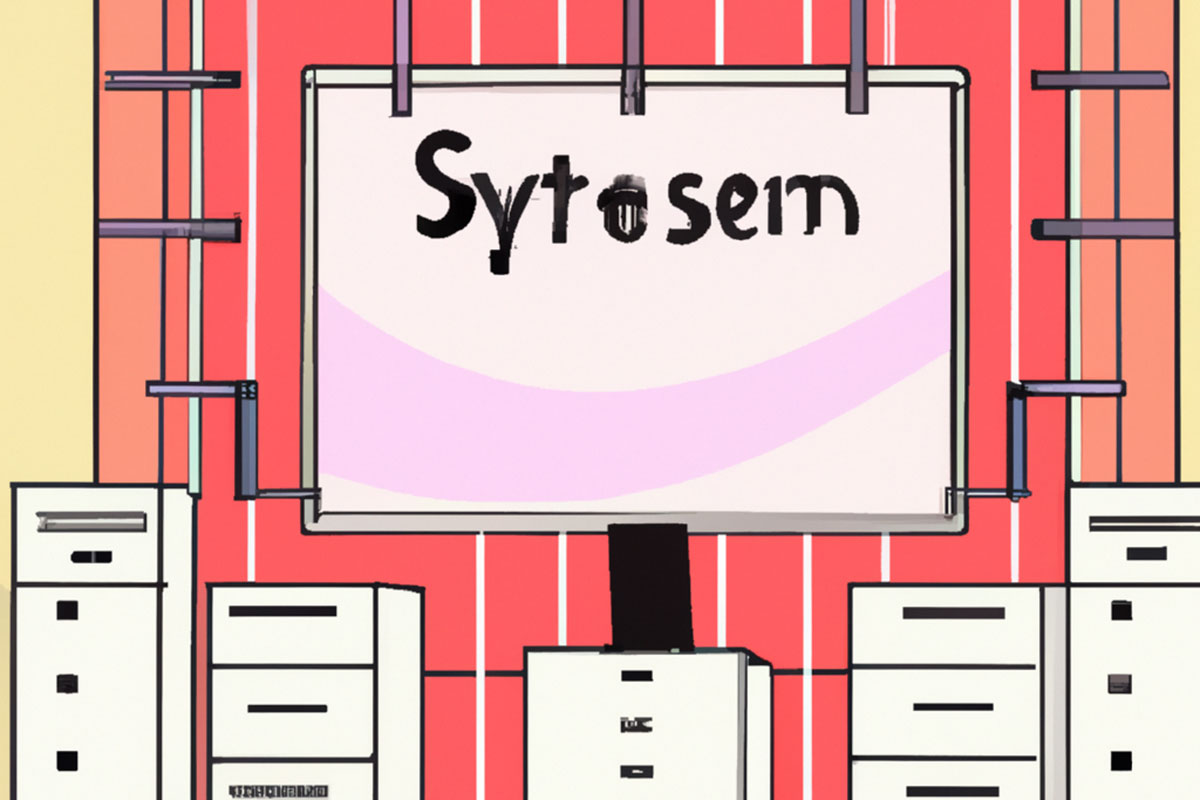
「オムニチャネル」とは
「オムニチャネルマーケティング」の「オムニ」は、ラテン語で「omni(全て)」という意味、
そして「チャネル」とは、商品やサービスを提供する手段や方法、販売のためのプラットフォームを指します。
チャネルの例としては、「店舗」「オンラインストア」「テレビショッピング」「カタログ販売」「モバイルアプリ」などがあります。
つまり、「オムニチャネルマーケティング」とは、「あらゆるプラットフォームのマーケティング」という意味になります。
企業が「オムニチャネルマーケティング」でできること
「オムニチャネルマーケティング」とは、消費者がどのようなチャネル(店舗、オンラインストア、モバイルアプリ、電話など)を通じてサービスに接触してきた場合でも、一貫性のある「体験」ができます。(または企業が、一貫性のある「体験」を提供することを目的としたマーケティング手法です)
企業に求められることは、一貫した「ブランド」です。
エントリーした「チャネル」によって、「サービス」が異なると不平等さから、クレームになります。
企業は、消費者がどの「チャネル」からエントリーしたときでも、なめらかで途切れのないシームレスなサービスを「体験」できるような、ブランディングを目指す必要があります。
そんな「オムニチャネルマーケティング」でできることについてまとめます。
1 複数のチャネルで一貫性のあるブランディング
「オムニチャネルマーケティング」では、複数のチャネルを通じて、ブランドの価値やメッセージを一貫して伝えることが重要です。
企業は、「店舗」「オンラインストア」「SNS」などすべてのチャネルで同じブランディングを使用し、顧客に「統一感」を与えます。
2 在庫の統合
「オムニチャネルマーケティング」では、在庫管理を統合することができます。たとえば、「店舗在庫」と「オンラインストア」の在庫を統合することで、在庫管理の負担を軽減し、在庫切れを防止することができます。
3 顧客データの共有
「オムニチャネルマーケティング」では、顧客が「店舗」「オンラインストア」「モバイルアプリ」などの複数のチャネルを使用して商品を購入した場合でも、それらのデータを共有することができます。また、共有できなければなりません。
これにより、より正確な顧客プロファイルを作成し、より個別化されたマーケティングを実施することができます。
4 シームレスな顧客体験の提供
「オムニチャネルマーケティング」では、顧客が複数のチャネルを使用して商品を購入する際に、シームレスな体験を提供することができます。
たとえば、オンラインストアで商品を見て店舗で実際に試着し、そのまま店舗で購入することができるようにできます。
「サービス」や「商品」の提供までをスムーズにします。
5 顧客ロイヤルティの向上
「オムニチャネルマーケティング」では、顧客が複数のチャネルを使用して商品を購入することができるため、顧客の「満足度」が向上し、「ロイヤリティ」が高まることが期待されます。
企業は、顧客がチャネルを切り替えても、一貫性のある「体験」を提供することで、利便性や満足度を高め、顧客ロイヤリティを向上させることができます。
また、顧客にとっては、複数のチャネルを利用することで、自分にとって最適な「購入方法を選択」できるため、顧客の選択肢も広がります。
6 マルチデバイスに対応したコンテンツ提供
「オムニチャネルマーケティング」では、顧客が複数のデバイスを使用して情報を収集することが一般的になっています。
企業は、「モバイルデバイス(スマートフォンやタブレット等)や「PC」など、さまざまなデバイスに対応したコンテンツを提供することで、顧客にとって最適な情報提供を行うことができます。
どのデバイスで、どんな情報提供をするか、が大事なところです。
7 チャネル同士の結合による促進
「オムニチャネルマーケティング」では、複数のチャネルを通じて、顧客に購入を促進することができます。
例えば、「オンラインストア」で商品を見た顧客に、「店舗」での購入を促すキャンペーンを行うことができたり、
あるいは、SNS広告から「店舗」に導くこともできます。
「オムニチャネルマーケティング」でできることは、幅広くありますが、逆にデメリットもあります。
デメリットについては、次のようなものが考えられます。
「オムニチャネルマーケティング」のデメリットは
消費者の購買満足度を促進させ、顧客ロイヤリティを高めるために有効な「オムニチャネルマーケティング」ですが、デメリットもあります。
1 実装コストが高い
まず「先行投資」が必要です。
「オムニチャネルマーケティング」を実装するためには、異なる販売チャネルに対応した、「テクノロジー」や「システム」また顧客と接触するまでの「プロセス」が必要になります。
また、それに伴う「広告」「プロモーション」「在庫管理」「顧客サポート」などのコストも発生する可能性がでてきます。
それらを導入し、稼働させるためには、高い費用がかかる場合があります。
2 プロセスの複雑さが生まれる
どのチャネルからエントリーした顧客でも、同じような「満足度」に導かなければなりません。
そのために、サービス提供までのプロセスが複雑化する可能性があります。
つまり「実店舗」や「オンラインストア」を統合したシステムと、プロセスを導入する必要があります。また、店舗スタッフは、オンラインストアの状態について把握しなければなりません。
ミスやトラブルを未然に防止するしくみが必要になります。
3 データの統合の問題
異なる販売チャネルを介して、顧客とやり取りする場合、「顧客データ」が複数の場所に分散している場合があります。
顧客のデータの統合を図らなければ、整合性が保てなくなるので注意が必要です。
4 チャネル間の競合
「オムニチャネルマーケティング」では、複数のチャネルを使用することが多いため、それぞれのチャネル同士が競合する可能性がでてきます。
例えば、
オンラインストアと実店舗の「価格競争」が起きたり、店舗在庫がオンラインストアの「在庫」と異なる場合などが生じたりする可能性があります。
オンラインと実店舗の価格や在庫に、「均一化」を図る必要がでてきます。
5 コンテンツの適合性の問題
チャネルに合わせた「コンテンツ」を提供する必要があります。
同じようにプロモーションしても、コンテンツがそのチャネルに適合していない場合は、効果が表れにくい可能性があります。
例えば、
「ターゲットの年齢層」がそのコンテンツを使っているか。
提供しているコンテンツが時代に合っているか。
「ターゲット」がコンテンツにリーチするまでの「難易度」は適切か。
などを考えて導入する必要があります。
「オムニチャネルマーケティング」の成功事例10
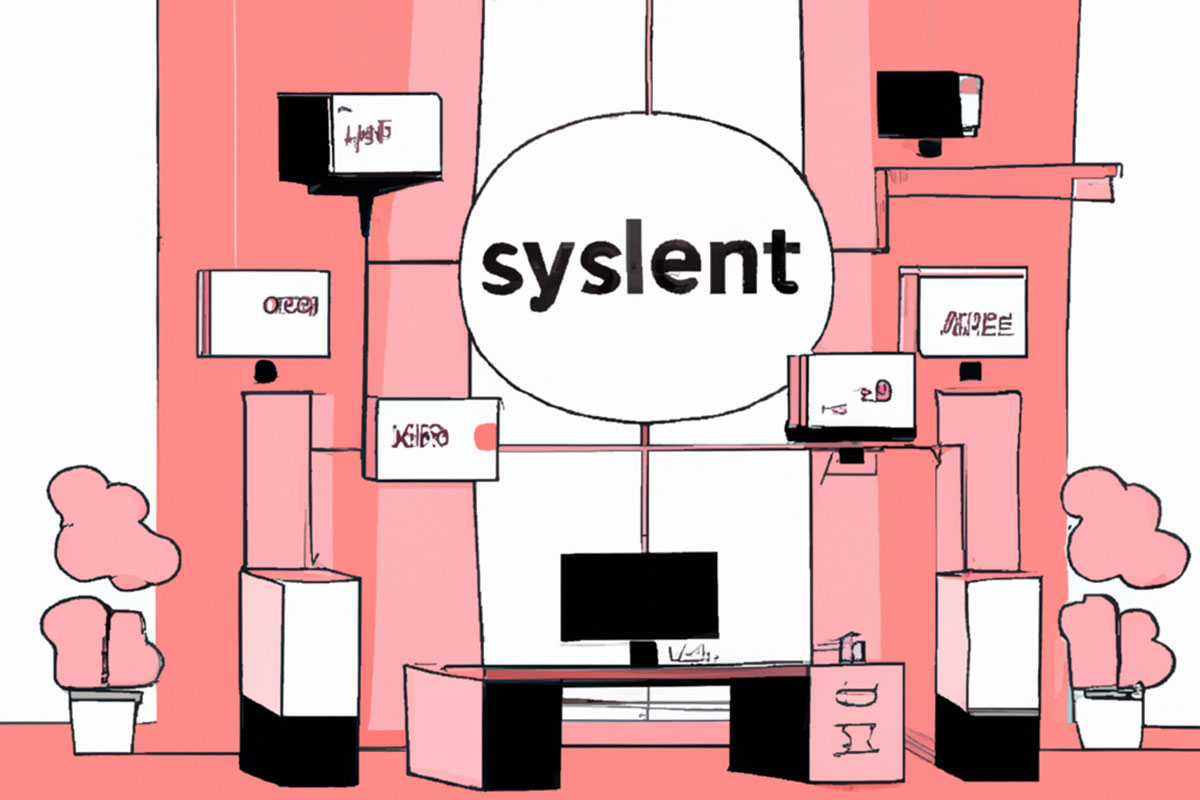
「オムニチャネルマーケティング」を使った企業の成功例を紹介します。
1 Zara(アパレルブランド)
Zaraは、オンラインストアと実店舗を統合したオムニチャネル戦略を展開しています。顧客は、オンラインストアで商品を購入し、店舗で商品の受け取りや返品ができます。
さらに、店舗で試着した商品をオンラインで購入することも可能です。
2 ウォルマート(小売企業)
ウォルマートは、店舗での買い物に加えて、オンラインストアやスマートフォンアプリを活用したオムニチャネル戦略を取り入れています。
店舗内で商品を購入する際に、スマートフォンでクーポンも利用できます。
3 マクドナルド(フードチェーン)
マクドナルドは、オンライン注文サイトやアプリを通じて、店舗での受け取りやデリバリーサービスを提供しています。
また、店舗内での注文にも専用のタッチパネルを導入し、顧客により便利な注文方法を提供しています。
4 フォード(自動車メーカー)
フォードは、顧客がディーラーで車を購入する前に、オンラインで車の詳細情報や見積もりを得ることができます。
また、車の整備や修理に関する情報もオンラインで提供しています。
5 ロウズ(ホームセンター)
ロウズは店舗での買い物だけでなく、オンラインストアやスマートフォンアプリを活用したショッピングサービスを提供しています。
オンラインストアで商品を購入した場合、店舗での受け取りや配送サービスも利用できます。
6 コカ・コーラ(飲料メーカー)
コカ・コーラは、自動販売機やスマートフォンアプリを活用し、消費者との接点を増やしています。
自動販売機で購入した商品の履歴を活用し、顧客に最適な商品の提案を行うことで、満足度の向上を図っています。
7 Apple(電子機器メーカー)
Appleは、オンラインストアと実店舗を統合し、顧客に最適な買い物体験を提供しています。
店舗での商品受け取りや、修理サービスをオンラインストアで予約することもできます。
8 ヨドバシカメラ(家電量販店)
ヨドバシカメラは、店舗での買い物だけでなく、オンラインストアやスマートフォンアプリを活用したショッピングサービスを提供しています。
店舗で商品を購入した場合、オンラインでの返品や交換が可能です。
9 JTB(旅行会社)
JTBは店舗での旅行予約に加えて、オンラインストアやスマートフォンアプリを活用した予約サービスを提供しています。
また、店舗での相談に加えて、オンラインでの相談やチャットサポートも提供しています。
10 NIKE(スポーツブランド)
NIKEでは、オンランストアと実店舗を統合し、顧客に最適な買い物体験を提供しています。店舗で試着した商品をオンラインで購入することができます。
また、オンラインストアで商品を購入した場合、店舗での受け取りや返品が可能です。
以上が、
「オムニチャネルマーケティング」の成功例です。
成功している企業は共通して、
オンラインコンテンツが生まれるよりも以前から、「消費者への接触のしかた」がうまかった、
または「そんな仕組みを持っていた」ように思います。
顧客の満足度やロイヤリティの向上を考えると、今後ますます普及していくことが予想されます。
「オムニチャネルマーケティング」を発想力で生かすなら
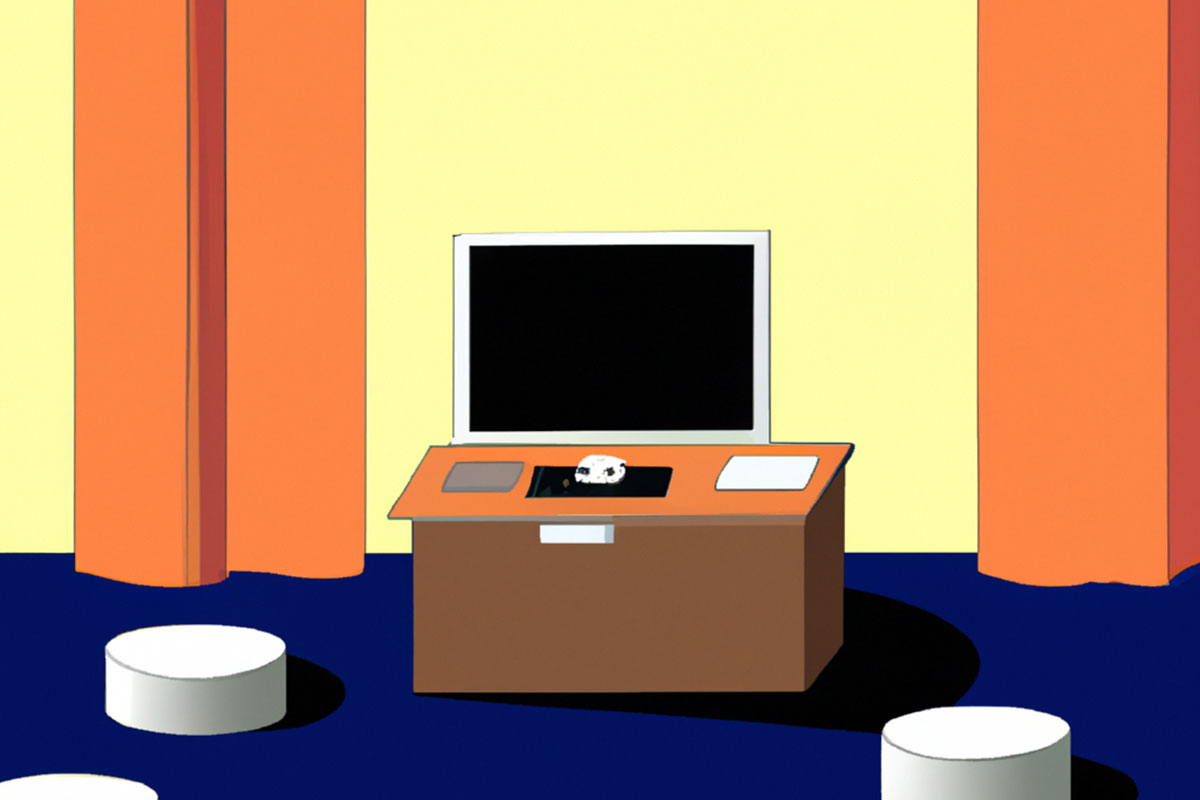
今や、いろいろな企業が「オムニチャネル」を活用した顧客の囲い込みに取り組んでいます。
これからも、この流れが続くことが予想されます。
今後の「オムニチャネルマーケティング」の活用アイデアについて考えてみます。
1 クロスチャネルでプロモーションをする
「オムニチャネルマーケティング」では、複数のチャネルを有機的(意味を持たせて)に結びつけることが重要です。
いろいろなチャネルを複合的にからませる「クロスチャネルプロモーション」を実施すること、より有効打が打てます。
例えば、
「オンラインでの購入」を促進するために「店舗でのキャンペーン」を実施したり、
「店舗での購入」を促進するために「オンラインストアでの割引クーポン」を配布するなどの双方を融合的に使うことで、効率的に成果につなげていきます。
また、店舗での購入に対して「オンラインアンケート」を行い、ユーザーニーズを掘り下げることもできます。
「クロスチャネルPR戦略」は、アイデア次第で効果が複利的に膨らみます。
2 マルチチャネル分析の実施
「オムニチャネルマーケティング」では、複数のチャネルを統合的に分析しなければなりません。
マルチチャネル分析をすることで、「顧客の行動パターン」や「購買履歴」を把握することができ、顧客への最適なアプローチをすることができます。
例えば、
「どこから顧客がやってきたのか」オンライン広告、SNS、メール、電話、実店舗を見た、などの行動分析や、
「何が一番目立っているのか」を知ることで、「広告費等の予算」を効果的に使うことができます。
3 AIの活用
AIを活用することで、顧客の「嗜好」や「ニーズ」をより正確に把握し、最適な商品やサービスを提供することができます。
また、AIを用いた自動化により、より迅速な反応が可能となります。
具体的には、顧客の「購買履歴」や「行動履歴」を分析し、適切な商品やサービスを提供する「リコメンド機能」や、「チャットボット」による問い合わせ対応などがあげられます。
ただ、AIは融通が効きにくい点もあるので、活用のための開発にはコストがかかる可能性があります。
4 ソーシャルメディアの活用
SNSは、複数のチャネルを有効に結びつけることができるツールです。
SNSは、現代のビジネスでは重要な役割を果たしています。
SNS上で、「情報発信」や「広告配信」を活用することで、オンラインストアや店舗への集客効果を高めることができます。
5 ARやVR技術の導入
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)の技術を導入することで、オンラインストアや店舗内での顧客体験を向上させることができます。
AR(拡張現実)も、VR(仮想現実)もシミュレーション世界を作り出すことです。それによって、ユーザーに先行体験してもらい、商品の「使用感」や「リッチさ」等を体感してもらうことができます。
例えば、AR技術を活用して、商品を立体的に見ることができる仕組みを導入することや、迷っている服を画面上で試着したり、購入する前に使用感を確認できるというメリットがあります。
6 インフルエンサーマーケティングの活用
最近、流行りの手法です。
インフルエンサーを活用することで、SNSを通じて商品やサービスを紹介し、商品やサービスの認知度を高めることができます。
また、オンラインストアや店舗での販売促進にもつながります。
7 カスタマージャーニーマップの作成
顧客の、購入までのプロセスがどのように進んでいるかを可視化します。
そうすることで、顧客の行動パターンやニーズを把握し、最適な施策を提供することができます。
例えば、顧客の「ユーザーエクスペリエンス(ユーザーの体験)」の快適度の度合いを高める方策が考えられたり、
製品やサービスを使うときの感情や意見などの情報まで集めることで、よりアップグレードした「パーソナライズサービス」を提供することができます。
8 モバイルマーケティングを活用する
現代では、だれもが持っているスマートフォン。
ほとんどのサイトで、モバイル端末からのアクセスが急増しています。
モバイルアプリやSNSを活用することで、顧客によりリアルタイムにアプローチすることが可能となっています。
\インフルエンサーマーケティング/
\ザ・元祖マーケティング/
発想力で決まる「オムニチャネルマーケティング」って何?【負けない仕組みづくりとは】 まとめ
今回は、「オムニチャネルマーケティング」についてまとめてみました。
現代のビジネスは、基本的には「法に基づいて、ありとあらゆる手段」を使用して、収益化することを考えなければなりません。
というより、「ありとあらゆる手段を使って収益化してもいいですよ」といったところでしょうか。
それには、「オンライン」と「オフライン」をうまく活用することが必要になります。
どんなビジネスにおいても「できること」はたくさんあります。
より効果的に集客したり、より効率的な収益化を目指すための仕組み作りは、どうすればよいのか、となると。
これは、誰もが簡単にできるものでもありません。
でも、ポイントはあります。
それは、「自社の強み」と「顧客満足度」
ここを向上させていくこと。
「顧客ニーズ」が「自社の強み」にフィットしたときは最高の瞬間です。
やはり、これに尽きるのではないでしょうか。
320
\進化を続けるマーケティング/






